なつめが乾燥されてからお客様に届くまで
なつめはクロウメモドキ科ナツメ属の果樹で、木に成った果実は緑から紅く熟すと生のままおいしく食べることができます。その味わいは酸味はほとんどなく淡白ながら優しい甘みを感じ、シャキシャキとしたリンゴやナシのような食感が心地よいフルーツです。一年のうちの10月前後の約1ヶ月間しか生なつめを味わうことができない極旬の味わいです。
生鮮なつめと乾燥なつめの栄養成分を比較すると、生鮮にはあって乾燥にはないもの、またその逆もあって、旬の時期にはぜひ生なつめを食べたいものです。らくだ道商店は長野県産の大粒生なつめの栽培にも関わっており毎年9月下旬頃より予約を受け付け多くの皆様に大変喜んでいただいております。農薬や化学肥料は使用しない自然栽培の天然大粒なつめです。

なつめが実って収穫されるのは9月から10月ですが、乾燥なつめは一年中市場に出回っています。世界最大の生産地である中国では広大な土地で年間数百万トンのなつめを生産しています。その中でも主要ななつめの生産地である新疆ウイグル自治区での収穫から乾燥を経て出荷、お客様まで届くまでをご紹介します。
秋の収穫期になると、オアシス地帯に広がる畑は、赤く色づいたなつめの実でいっぱいになります。タクラマカン砂漠が広大な面積を占めるこの地域では昼夜の寒暖差、強い日差し、乾いた空気が、糖度の高いなつめを育みます。熟した実は一つひとつ手摘みで集められ、時には枝を叩いて落とす方法も用いられます。その後、傷の有無や大きさで丁寧に選別され、乾燥の工程へ。

新疆では昔から「天日干し」が主流でした。澄んだ青空の下、広場や棚に赤い実を並べ、砂漠の乾いた風と太陽の光でじっくり約2週間水分を飛ばします。これにより、果実の甘みが凝縮し、保存性も高まります。近年は熱風乾燥機を使って均一に仕上げる方法も普及しましたが、伝統的な天日干しの風味を好む人も少なくありません。
その昔、新疆を通るシルクロードを行き来したキャラバンにとって、なつめは大切な保存食でした。長い旅に耐えられるよう、果実を硬くなるまで乾燥させて持ち運びます。硬いままでは食べにくいため、彼らは工夫をこらしました。例えば、水筒の水に浸して一晩かけて少しずつ戻したり、蒸気で柔らかくしたり。時には蜂蜜水に漬けて甘みを加え、おやつ代わりに楽しんだともいわれています。乾燥なつめは、過酷な砂漠の旅を支えるエネルギー源だったのです。
今では冷蔵・冷凍設備や真空パック、窒素充填といった技術により、一年を通して新疆なつめを楽しむことができます。けれども、太陽の下で乾燥させたなつめには、昔ながらの保存食としての魅力が残っています。水に浸して数日かけて戻せば、ふっくらと蘇り、スープや薬膳料理に深みを与えてくれます。
その一粒を口にするたびに、はるか昔、シルクロードを行き交ったキャラバンの姿を思い浮かべてみてはいかがでしょうか。
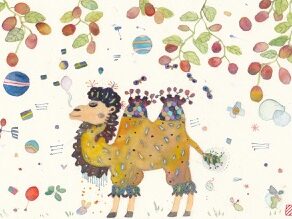
投稿者プロフィール

最新の投稿
 なつめの魅力2025年10月4日【ご予約受付中】2025年度産・長野県産 無農薬大粒なつめ
なつめの魅力2025年10月4日【ご予約受付中】2025年度産・長野県産 無農薬大粒なつめ なつめの魅力2025年9月20日2025年度産 長野県産大粒生なつめ
なつめの魅力2025年9月20日2025年度産 長野県産大粒生なつめ なつめの魅力2025年9月10日初めてのなつめ
なつめの魅力2025年9月10日初めてのなつめ なつめの魅力2025年9月8日デーツとなつめ その違い知っていますか?
なつめの魅力2025年9月8日デーツとなつめ その違い知っていますか?


